「先月の電気代、請求額を見て驚愕した…」「在宅勤務で一日中エアコンを使っているけど、電気代が心配」「つけっぱなしの方が安いって聞くけど、本当なの?」
夏の猛暑や冬の厳しい寒さを乗り切るために不可欠なエアコン。しかし、その一方で家計を圧迫する電気代の悩みを抱えている方は少なくありません。特に、在宅ワークのように、日中の大半を自宅で過ごす方にとって、エアコンの電気代は切実な問題です。
ご安心ください。エアコンの電気代は、仕組みを正しく理解し、ご自身のライフスタイルに合った工夫を組み合わせることで、無理なく、そして賢く節約することが可能です。
この記事では、電気代の基本的な計算方法から、誰もが気になる「つけっぱなし」の真実、そして明日からすぐに実践できる具体的な節約術まで、専門的な知見を交えて徹底的に解説します。さらに、在宅ワーカーやペットのいるご家庭といったライフスタイル別の最適な方法や、長期的な視点での根本対策まで網羅。
この記事を読み終える頃には、あなたはエアコン電気代の専門家となり、もう電気代の請求に怯えることなく、一年中快適な室内環境を手に入れているはずです。
- エアコンは起動時が一番電力を使うため、短時間の外出ではつけっぱなしの方が節約になる
- 自動運転モードが最も効率的で、手動調整より最大26%も電力を節約できる
- 設定温度を1℃調整するだけで冷暖房それぞれ10%以上の節電効果が期待できる
- 古いエアコンは年間で数千~数万円の無駄。買い替え+補助金活用が節約の近道
- 電気代はライフスタイルに合ったプラン選びで大きく変わる。見直さないと損!
エアコンの電気代が高いのは、つけ方や使い方に「もったいない」が潜んでいるから。この記事では、電気代がどう決まるのかという基本から、「つけっぱなしvsこまめに消す」の正しい判断、そして今すぐ実践できる節約術を30個も紹介。フィルター掃除や風量設定の工夫だけでも数%の節電につながります。さらに、在宅勤務やペットのいる家庭、木造住宅などの環境別に最適な方法も解説。最後には、省エネエアコンへの買い替えや電力プランの見直しといった、長期的にお得になる根本対策も取り上げています。
あなたの無駄遣いはどこ?エアコンの電気代セルフチェック
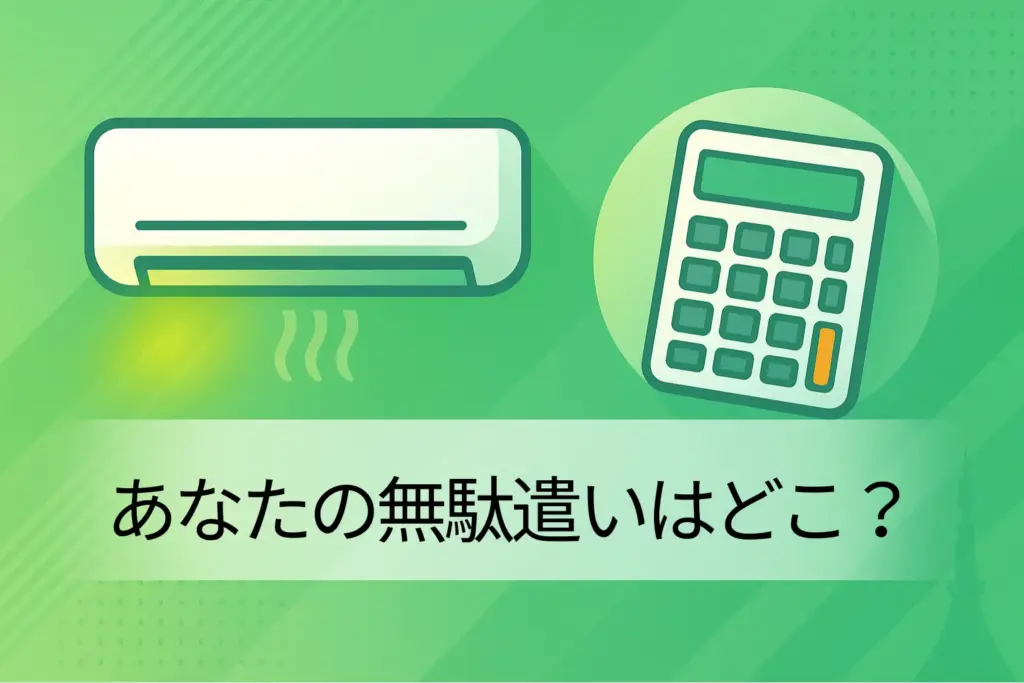
まずは、現在のエアコンの使い方に無駄が潜んでいないか、簡単なチェックリストで確認してみましょう。3つ以上当てはまった方は、この記事を読むことで電気代を大幅に削減できる可能性があります。
💡 エアコン使い方セルフチェック
あなたの節電レベルをチェックしましょう(チェックボックス形式)
いかがでしたか?それでは、なぜこれらが無駄遣いに繋がるのか、その理由と具体的な解決策を詳しく見ていきましょう。
【知識編】なぜ高い?エアコン電気代の基本
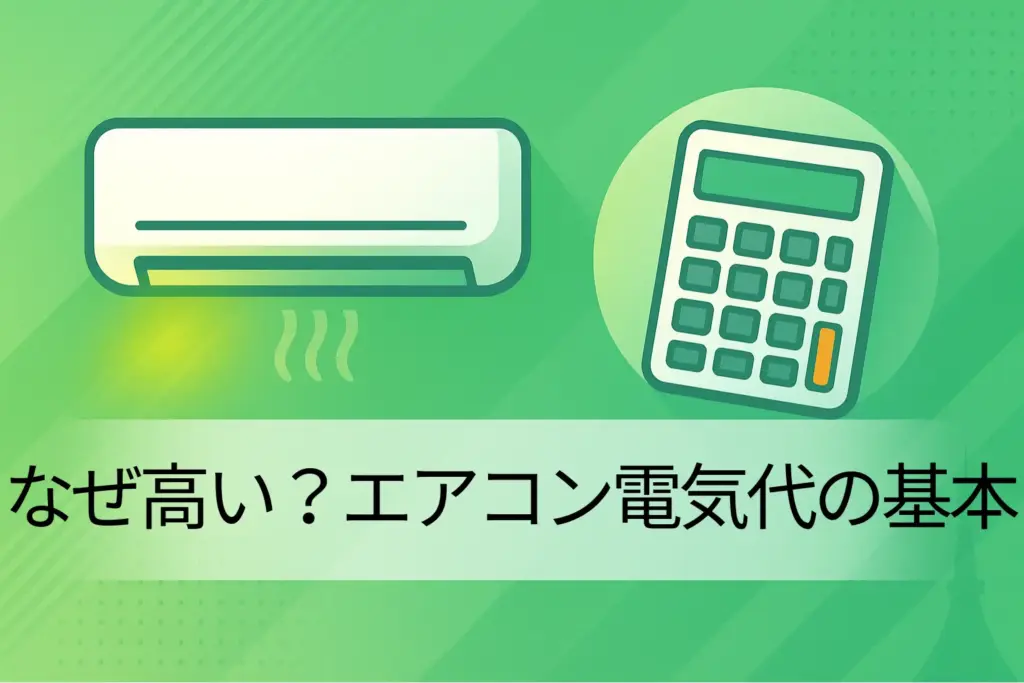
効果的な節約術を実践するためには、まずエアコンの電気代がどのように決まるのか、その基本を理解することが重要です。
エアコンの電気代が決まる仕組み
エアコンの電気代は、非常にシンプルな式で計算できます。
電気代 = 消費電力(kW) × 使用時間(h) × 電気料金単価(円/kWh)
ここで重要なのが「消費電力(kW)」です。実は、エアコンの消費電力は常に一定ではありません。最も電力を消費するのは、スイッチを入れた直後です。設定温度と室温に大きな差がある場合、エアコンはフルパワーで稼働し、室温を一気に調整しようとします。
そして、部屋が設定温度に近づくと、消費電力はグッと下がり、安定運転に移行します。この「起動時」の大きな電力をいかに減らすかが、節約の第一歩となります。
1時間・1ヶ月の電気代の目安はいくら?
では、実際の電気代はどのくらいなのでしょうか。エアコンの性能や部屋の広さによって大きく異なりますが、一般的な目安を下の表にまとめました。ここでは、最新の省エネモデルと10年前の旧式モデルを比較しています。
| 部屋の広さ | エアコンの種類 | 1時間あたりの電気代(目安) | 1ヶ月の電気代(目安) |
|---|---|---|---|
| 6畳 | 最新省エネモデル | 約2.5円~15.5円 | 約600円~3,720円 |
| 10年前のモデル | 約4.7円~24.8円 | 約1,128円~5,952円 | |
| 12畳 | 最新省エネモデル | 約2.6円~32.6円 | 約624円~7,824円 |
| 10年前のモデル | 約4.8円~52.7円 | 約1,152円~12,648円 | |
| 16畳 | 最新省エネモデル | 約2.8円~46.5円 | 約672円~11,160円 |
| 10年前のモデル | 約5.5円~77.5円 | 約1,320円~18,600円 |
※電気料金単価31円/kWh(税込)で計算。1日8時間、30日間使用した場合。
※消費電力は各メーカーのカタログ記載の最小・最大値を参考に算出。
この表から、最新の省エネエアコンは旧式に比べて電気代を大幅に抑えられることが一目瞭然です。特に、在宅勤務で長時間利用する佐藤さんのようなケースでは、その差は年間で数万円に達することもあります。
「冷房」「暖房」「除湿」一番電気代が高いのは?
エアコンには様々な運転モードがありますが、電気代はどのモードが最も高いのでしょうか。一般的に、消費電力が大きい順に並べると以下のようになります。
暖房 > 冷房 > 除湿(弱冷房式)
最も電気代が高いのは「暖房」です。これは、冬場に外気温(例えば5℃)と設定温度(例えば20℃)の差が大きいのに対し、夏場は外気温(例えば35℃)と設定温度(例えば28℃)の差が比較的小さいためです。エアコンは温度差が大きいほど多くのエネルギーを必要とするため、暖房運転時の方が消費電力が大きくなるのです。
また、「除湿」には種類があり、室温を下げずに湿度だけ取る「再熱除湿」は、冷房よりも電気代が高くなることがあるため注意が必要です。
- 電気代は「何時間使ったか」よりも「どう起動させたか」で決まる
- 実際はこまめなオンオフが電力ロスの元になることも
- 10年前のエアコンは最新機種の約1.5倍の電力を消費することも
- 暖房の方が電気代がかかるのは、外気温との差が大きいから
【実践編・基本】効果絶大!今すぐできる王道の節約術10選
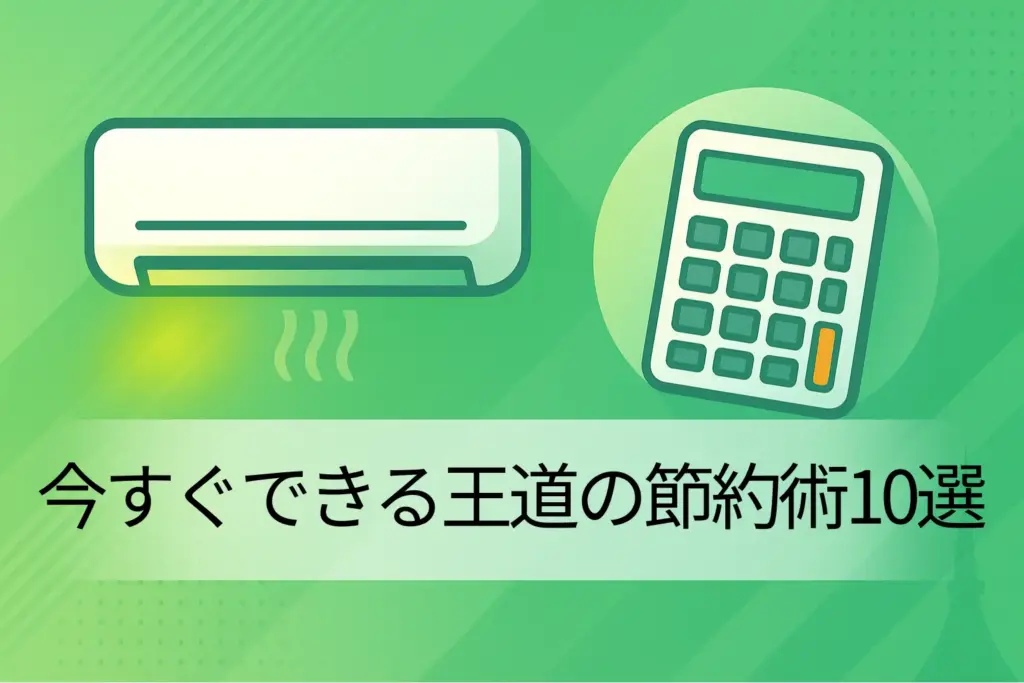
エアコン電気代の基本を理解したところで、いよいよ実践編です。ここでは、誰でも簡単に取り組める効果の高い節約術を厳選してご紹介します。
「つけっぱなし」vs「こまめに消す」論争の最終結論
「つけっぱなしの方が安い」という話、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。これは、半分正解で半分間違いです。結論から言うと、「30分〜1時間程度の短い外出であれば、つけっぱなしの方がお得」な場合が多いです。
これは、Part1で説明した通り、エアコンは起動時に最も多くの電力を消費するためです。こまめに電源をオンオフすると、その都度フルパワーで運転を開始するため、結果的に消費電力が積み重なってしまいます。
一方、つけっぱなしであれば、室温が安定した後は少ない電力で運転を維持できます。在宅勤務中の昼休みなど、短時間の外出では電源を切らない方が賢明と言えるでしょう。
最適解は「自動運転」!風量設定の罠
電気代を気にして、つい風量を「弱」に設定していませんか?実はこれが大きな落とし穴です。「弱」で運転すると、設定温度になるまでに時間がかかり、かえって無駄な電力を消費してしまうことがあります。
最も効率的なのは「自動運転」モードです。自動運転は、室温を最も効率的に設定温度に近づけるよう、AIが風量を自動で調整してくれます。起動時は強風で一気に室温を調整し、その後は微風で温度をキープするため、手動で設定するよりも無駄なく快適な空間を維持できるのです。
ある調査では、手動で調整するよりも約26%も消費電力を削減できるという結果も出ています。
設定温度は「1℃」が命運を分ける
節約の基本中の基本ですが、設定温度の調整は非常に効果的です。環境省は室温の目安として冷房時28℃、暖房時20℃を推奨していますが、これを基準に「冷房は1℃高く、暖房は1℃低く」設定するだけで、大きな節約効果が期待できます。
具体的には、設定温度を1℃変えるだけで冷房時で約13%、暖房時で約10%の消費電力削減に繋がると言われています。無理のない範囲で、まずは0.5℃からでも調整を試してみてください。体感温度は、後述するサーキュレーターの併用などで十分にカバーできます。
フィルター掃除は2週間に1回が鉄則
面倒に感じがちなフィルター掃除ですが、その効果は絶大です。フィルターにホコリが詰まると、エアコンは空気を吸い込みにくくなり、部屋を冷やしたり暖めたりするためにより多くのパワーが必要になります。
2週間に1回のフィルター掃除を実践するだけで、冷房時で約4%、暖房時で約6%の消費電力を削減できるというデータがあります。掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどい場合は水洗いするだけでOKです。これだけで電気代が安くなるだけでなく、エアコンから送られる空気が清潔になり、健康面でもメリットがあります。
室外機の環境改善で効率アップ
室内機と同じくらい重要なのが、屋外に設置されている「室外機」です。室外機は、室内の熱を外に逃がす(冷房時)または外の熱を取り込む(暖房時)という重要な役割を担っています。
室外機の吹き出し口の周りに物を置いていると、熱交換の効率が下がり、無駄な電力を使ってしまいます。室外機の周りは常に整理整頓を心がけましょう。また、夏場に直射日光が当たっている場合は、「日除け(サンシェード)」を設置するのがおすすめです。
これにより室外機の温度上昇が抑えられ、約5%の消費電力削減に繋がります。
サーキュレーター・扇風機併用術
設定温度を無理に下げなくても、涼しく感じる秘訣が「サーキュレーター(または扇風機)」の併用です。空気を循環させることで室内の温度ムラがなくなり、体感温度を下げることができます。
これにより、エアコンの設定温度を1〜2℃上げても快適に過ごすことができ、約20%もの消費電力削減が期待できます。
使い方のコツは、冷房時はエアコンに背を向けるように床に置き、上向きに風を送ること。冷たい空気は下に溜まる性質があるため、これを循環させることで部屋全体が涼しくなります。
逆に暖房時は、エアコンの対角線上に置き、上に向けて風を送ると、上に溜まりがちな暖かい空気を足元に届けられます。
窓の断熱対策で熱の出入りを防ぐ
エアコンがいくら頑張っても、窓から熱が出入りしていては効率が落ちてしまいます。特に夏は外からの熱気の約7割が、冬は室内の暖気の約5割が窓から出入りすると言われています。
遮光・断熱効果の高いカーテンに替えたり、窓に断熱シートを貼ったりするだけで、冷暖房の効率は大きく向上します。レースカーテンを日中も閉めておくだけでも効果があります。こうした地道な対策が、結果的に電気代の節約に繋がるのです。
タイマー機能の賢い使い方
エアコンのタイマー機能を活用することで、生活リズムに合わせた無駄のない運転が可能です。特に就寝時は、「おやすみタイマー」や「切タイマー」が役立ちます。
例えば、就寝の1時間後に電源が切れるようにセットすれば、寝付いた後のつけっぱなしを防げます。暑くて目が覚めてしまう場合は、起床時間の1時間前に電源が入るように「入タイマー」をセットしておくのも良いでしょう。
これにより、快適な睡眠と電気代の節約を両立できます。
各メーカーの「省エネモード」を使いこなす
最近のエアコンには、各メーカーが独自に開発した「省エネモード」や「エコモード」が搭載されています。これらのモードは、人感センサーや日射センサーなどを活用し、人の在室状況や部屋の環境に合わせて自動で最適な省エネ運転を行ってくれます。
例えば、ダイキンの「AI快適自動運転」やパナソニックの「エオリアAI」などは、気象情報と連携して未来の室温を予測し、先回りして運転を制御する高度な機能を備えています。お使いのエアコンの取扱説明書を確認し、これらの機能を積極的に活用しましょう。
ドレンホースの詰まりをチェック
見落としがちですが、エアコンの水を外部に排出するための「ドレンホース」のチェックも重要です。このホースの先端がゴミや泥で詰まっていると、室内機からの水漏れの原因になるだけでなく、エアコンの運転効率を低下させることもあります。
定期的にホースの先端が汚れていないか、水がスムーズに排出されているかを確認しましょう。もし詰まりが見つかった場合は、古い歯ブラシなどで優しくゴミを取り除いてください。
- 自動運転はセンサー制御により温度・湿度・気流を同時に最適化するため、最も高効率
- フィルターの目詰まりは風量低下→冷媒圧力上昇→電力過剰消費という負の連鎖を引き起こす
- 「弱風運転」は快適だが効率が悪く、エアコンの定格性能を活かせない
【実践編・応用】ライフスタイル・住宅別 最適節約術

基本的な節約術に加えて、ご自身の生活環境に合わせた工夫を取り入れることで、さらに高い節約効果が期待できます。
在宅ワーカー(日中つけっぱなし)の最適解
ペルソナの佐藤さんのように、在宅勤務で日中もエアコンを稼働させている方には、特別な工夫が必要です。基本は「つけっぱなし」の方がお得ですが、日中の日差しが強い時間帯は、遮光カーテンを閉めて室温の上昇を防ぐことが特に重要になります。
また、お昼休憩で少し長めに家を空ける(1時間以上)場合は、一度電源をOFFにしましょう。短時間の外出と長時間の外出で、オンオフを使い分ける意識が大切です。
ペットや赤ちゃんがいる家庭の注意点
ペットや赤ちゃんがいるご家庭では、安全と快適性を最優先に考える必要があります。24時間エアコンを稼働させることも多いでしょう。その場合の節約ポイントは、設定温度を無理に下げすぎないこと。
例えば、ペットのためなら冷房を27〜28℃程度に設定し、サーキュレーターを併用して空気を循環させることで、効率的に快適な環境を維持できます。
赤ちゃんのいる部屋では、エアコンの風が直接当たらないように風向きを調整する配慮も忘れないようにしましょう。
【住宅別】木造戸建ての節約ポイント
佐藤さんがお住まいの木造戸建ては、一般的に鉄筋コンクリート造のマンションに比べて気密性・断熱性が低い傾向があります。そのため、外気の影響を受けやすく、エアコンの負荷も大きくなりがちです。特に窓や壁からの熱の出入りをいかに防ぐかが重要になります。Part2で紹介した窓の断熱対策は必須と言えるでしょう。
さらに、冬場は厚手のラグを敷いたり、ドアの隙間に隙間テープを貼ったりすることで、室内の暖気を逃がさない工夫が効果的です。
【住宅別】賃貸アパート・マンションの注意点
賃貸物件にお住まいの場合、エアコンが備え付けであるケースがほとんどです。最新の省エネモデルではない可能性も高いため、できる範囲での節約術を徹底することが大切です。フィルター掃除や室外機の環境整備、サーキュレーターの併用といった基本的な対策は、どのような機種でも効果を発揮します。
また、ごく稀に建物全体で電力会社と一括契約している「高圧一括受電」の場合があり、その際は個人で電力会社を選ぶことができません。乗り換えを検討する際は、まず管理会社や大家さんに確認しましょう。
- 室温よりも「床温」が快適性に直結──温度計ではなく体感を基準にすることが重要
- ペットは人より低い位置にいるため、サーキュレーターの併用で上下の温度ムラを防ぐのが有効
- 体調管理が難しい赤ちゃんには、湿度と風速の制御が大切(直接風を当てない+加湿併用)
- 内窓・遮熱フィルム・断熱カーテンなど、物理的な熱遮断が電気代に直結する
- 賃貸住宅は構造的制約が多いため、“貼ってはがせる”簡易対策の活用がコスパ◎
【根本解決編】長期的な視点で考える電気代対策
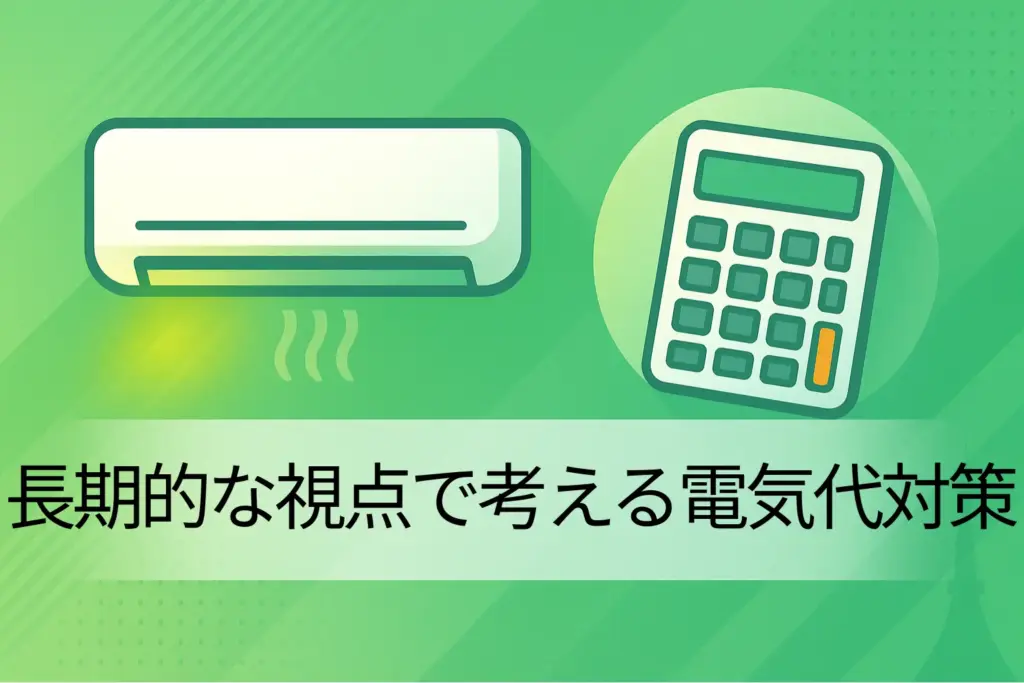
日々の工夫も大切ですが、時には根本的な見直しが大きな節約に繋がります。ここでは、長期的な視点での対策をご紹介します。
省エネエアコンへの買い替えは何年で元が取れる?
もし10年以上前のエアコンをお使いなら、買い替えが最も効果的な節約術になる可能性があります。最新の省エネエアコンは技術が飛躍的に進歩しており、10年前の同等クラスの機種と比較して、年間の電気代が数千円から数万円安くなることも珍しくありません。
エアコンの省エネ性能は「APF(通年エネルギー消費効率)」という数値で示されます。この数値が高いほど省エネ性能が高く、電気代が安くなります。初期費用はかかりますが、例えば年間2万円電気代が安くなれば、15万円のエアコンでも7〜8年で元が取れる計算になります。
長期的に見れば、買い替えは非常に賢い投資と言えるでしょう。
買い替え前にチェック!補助金制度の活用法
省エネエアコンへの買い替えを後押しするため、国や自治体は様々な補助金制度を用意しています。例えば、国の事業である「子育てエコホーム支援事業」では、省エネ性能の高いエアコンの設置に対して補助金が支給されます。
参考:https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp
また、東京都の「東京ゼロエミポイント」のように、自治体独自の制度も数多く存在します。これらの補助金を活用すれば、買い替えの初期費用を大幅に抑えることが可能です。買い替えを検討する際は、必ずお住まいの自治体のホームページや、事業の公式サイトを確認してみてください。
電力会社のプラン見直しで固定費を削減
2016年の電力自由化以降、私たちはライフスタイルに合わせて電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。しかし、一度もプランを見直したことがないという方も多いのではないでしょうか。
例えば、日中に電気を多く使う在宅ワーカーなら昼間の料金が安いプラン、夜間に電気を使うことが多いなら夜間割引プランといったように、ご自身の生活パターンに最適なプランを選ぶことで、電気代という固定費を大きく削減できる可能性があります。「エネチェンジ」や「価格.com」といった比較サイトを使えば、簡単に料金シミュレーションができます。
契約アンペア数、見直したことありますか?
電力会社のプランと合わせて見直したいのが「契約アンペア(A)数」です。これは、一度に使える電気の量を決めるもので、この数値によって毎月の「基本料金」が変わります。
| アンペア数 | 目安 |
|---|---|
| 20A | 電気をあまり使わない一人暮らし |
| 30A | 一人暮らし、二人暮らし |
| 40A | 二人暮らし、三人暮らし |
| 50A~60A | 家族の人数が多い、または電気使用量が多い家庭 |
もし、ご自身のライフスタイルに対して契約アンペア数が大きすぎると、使ってもいない電気の基本料金を毎月払い続けていることになります。逆に、頻繁にブレーカーが落ちる場合はアンペア数が足りていません。電力会社のウェブサイトや検針票で現在の契約アンペア数を確認し、適切かどうか一度見直してみることをおすすめします。
- 国や自治体の補助金・省エネポイントは買い替えのハードルを一気に下げる効果あ
- 最新型エアコンはセンサー・AI搭載による空間最適化で、従来型より圧倒的に省エネ
- 契約容量(kVA/アンペア)に応じた固定費を見直すべき
- 契約プラン(従量電灯/時間帯別など)と生活リズムが合っていないと損するケースが多い
エアコンの電気代に関するQ&A
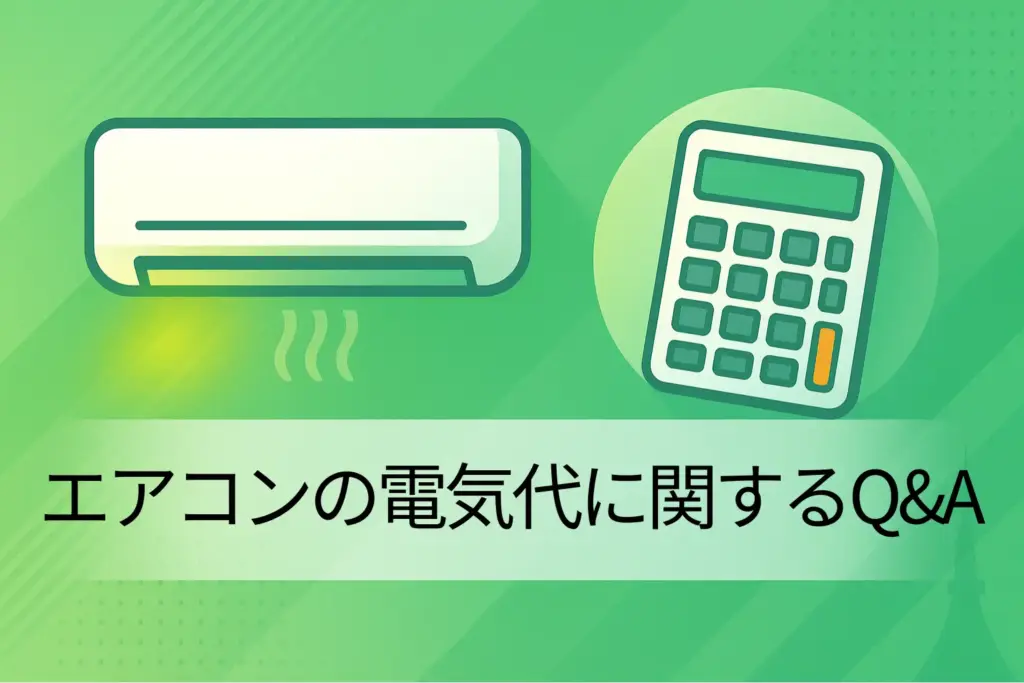
エアコンを1日つけたら電気代はいくらかかりますか?
エアコンを1日中つけたときの電気代は、使い方や機種、部屋の広さによって異なりますが、一般的な家庭用エアコン(冷房・10畳・省エネタイプ)を1日8時間使用した場合、おおよそ150円〜250円程度が目安です。
たとえば「弱風で設定温度27℃」のように省エネ運転を心がければ150円前後で済むこともありますが、外気温が高くフル稼働状態になれば1日300円近くになることもあります。
一日中「つけっぱなし」で24時間運転すると、1日400〜600円程度かかることもあるため、断熱・遮熱・サーキュレーター併用などで効率的に使うことが節電のポイントです。
エアコン1時間で何円かかりますか?
エアコンを1時間使ったときの電気代は、一般的な家庭用エアコン(10畳用・冷房)で約3〜10円程度です。
電気代に差が出る理由は、以下のような要因があるからです。
- 室温と設定温度の差が大きいと消費電力が増えます
- 運転開始直後は電力消費が多く、一定温度になると抑えられます
- 冷房よりも暖房の方が高くなることがあります
- 弱運転や省エネモードでは1時間あたり3〜5円程度に抑えられることもあります
つまり、涼しい日であれば1時間あたり3円前後、真夏でフル稼働なら10円近くになると考えておくとよいでしょう。
エアコンで一番安い設定は?
エアコンで電気代が一番安くなる設定は、「温度は高め(冷房なら27〜28℃)、風量は弱めか自動、風向きは水平、扇風機やサーキュレーター併用」です。
エアコンは、室温と設定温度の差が大きいほど多くの電力を使います。つまり、設定温度を低くしすぎると電気代が跳ね上がります。逆に、冷やしすぎず風を効率よく回すことで、消費電力を最小限に抑えることができます。
また、つけたり消したりを繰り返すよりも、つけっぱなしで安定運転を続けたほうが電気代が安くなることもあるため、外出時間が短い場合は切らずに使うのもコツです。
エアコンの暖房運転の電気代は1時間いくらですか?
エアコンの暖房を1時間使ったときの電気代は、おおよそ10円〜20円程度が目安です。
冷房に比べて暖房は消費電力が高くなる傾向があります。理由は、外の気温が低いときに室内を温めるには、より多くのエネルギーが必要になるからです。特に真冬で外気温が5℃以下になると、暖房効率が下がり電気代がかさむこともあります。
また、設定温度が高すぎたり、部屋が広かったり断熱性が低い場合も、電気代は高くなります。目安として、省エネ機種で設定温度20℃・風量自動の場合は約10〜13円、寒冷地やフル稼働時には20円以上かかることもあります。効率よく使うには、加湿・断熱カーテン・こたつとの併用なども効果的です。
エアコンの温度は何度にすれば安いですか?
エアコンの電気代を安くしたいなら、冷房時は27〜28℃、暖房時は20℃くらいが最もおすすめです。
冷房の設定温度を1℃高くすると、電気代は約10%節約できると言われています。たとえば、25℃設定を28℃に変えるだけでもかなりの節電効果があります。逆に、冷やしすぎはムダな電力消費につながります。
暖房の場合も同様で、設定温度が高いほど消費電力が増えます。20℃くらいに設定して、あとは加湿器や断熱対策、ひざ掛けなどで体感温度を上げる工夫をすると快適さと節電の両立ができます。
つまり、「冷房は高め」「暖房は低め」が節電の基本です。
暖房は何時間ならエアコンを消すべきですか?
エアコンの暖房は、2時間以上部屋を空けるなら消したほうが電気代は安くなります。
短時間(1時間以内)の外出なら、再稼働時の電力消費を考えるとつけっぱなしのほうが安くすむ場合もあります。暖房は立ち上がり時に多くの電力を使うため、こまめにオンオフを繰り返すと逆に高くつくこともあります。
ただし、長時間留守にするなら、暖まりすぎによるムダ遣いや安全面の観点からも電源を切るのが基本です。再度帰宅時に素早く暖めたい場合は、タイマー予約やスマートリモコンを使うと効率的です。
暖房の22度は何円?
エアコンの暖房を22℃に設定して1時間使った場合の電気代は、だいたい12円〜18円程度です。
この金額は以下の条件で変動します。
- 外気温が低いほど、暖めるための消費電力が増えます
- 部屋の断熱性が低いと、熱が逃げて余計に電力がかかります
- エアコンの年式や省エネ性能でも違いが出ます
たとえば、省エネタイプのエアコンで気密性の高い10畳の部屋なら、1時間あたり約12〜14円程度。一方、古い機種や寒冷地などでエアコンがフル稼働すると18円以上かかることもあります。
つまり、22℃設定は暖かさと電気代のバランスがよく、快適に過ごしながらも節約しやすい温度と言えます。
エアコンを安く使う方法はありますか?
はい、エアコンを安く使う方法はたくさんあります。特に意識するだけで効果が大きいのは次のような工夫です。
まず、冷房は27〜28℃、暖房は20℃くらいの設定温度にするのが基本です。これだけで電気代がグッと下がります。さらに、風量は「自動」に設定し、風向きを水平にすると効率よく部屋全体に空気が循環します。
また、サーキュレーターや扇風機を併用して空気を循環させることで、設定温度を変えずに体感温度を調整できます。フィルター掃除を月1回は行うことも忘れずに。ほこりがたまると冷暖房効率が落ちてムダな電力がかかります。
さらに、日中はカーテンやブラインドで直射日光を遮る/夜は断熱カーテンで熱を逃がさないといった対策も重要です。
短時間の外出ならエアコンはつけっぱなしの方が安い場合が多いので、こまめに切るのではなく、2時間以上空けるときだけ電源を切るのがベストです。
エアコンは夏と冬どっちが高い?
一般的に、エアコンの電気代は冬(暖房)の方が高くなりやすいです。
その理由は、暖房時は外の気温が低いため、室温との温度差が大きくなり、より多くの電力を使って温める必要があるからです。特に外気温が5℃以下になるとエアコンは効率が下がり、消費電力が増えます。
一方、夏の冷房は冷やすだけなので、消費電力は冬ほど大きくありません。冷房は設定温度を高め(27~28℃)にして、サーキュレーターを併用すれば、効率的に涼しくできます。
つまり、同じ時間使ったとしても、冬の暖房の方が電気代が高くなりやすいのが一般的です。
エアコンの価格はいつが一番高いですか?
エアコンの価格が一番高くなるのは、夏の直前(6月〜7月)と冬の直前(11月〜12月)です。
この時期はエアコンの需要が一気に高まり、家電量販店も値引きよりも販売重視になるため、価格が上がりやすくなります。特に猛暑や寒波の予報が出ると、駆け込み購入が増えて、在庫不足や工事待ちも発生し、値下げの余地がなくなります。
逆に安く買える時期は、在庫処分が始まる8月下旬〜9月、または2月〜3月の決算期です。この時期は型落ちモデルの値下げもあり、価格交渉もしやすくなります。
つまり、「みんなが買う前に買う」のが価格を抑えるコツです。
エアコンの電気代まとめ
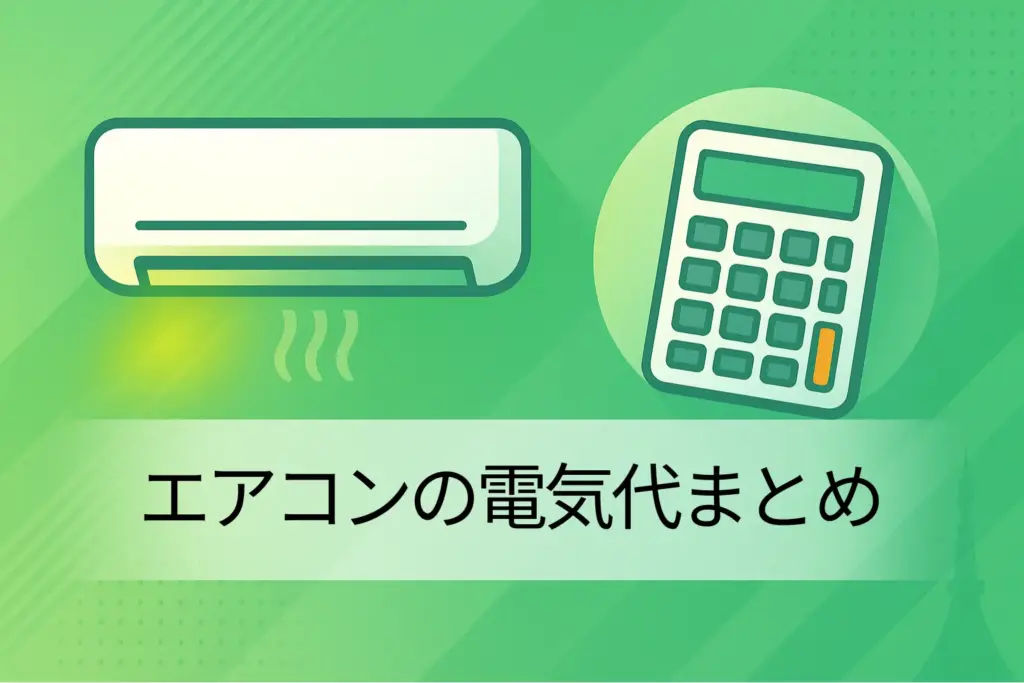
エアコンの電気代は、「仕組みの理解」「日々の正しい使い方」「長期的な視点での対策」という3つのアプローチを組み合わせることで、確実に削減できます。これまで解説してきた数々の節約術は、一つひとつは小さな工夫かもしれませんが、積み重ねることで大きな成果に繋がります。
最後に、この記事を読んだあなたが今日からすぐに実践できるアクションリストを3つ提案します。
- エアコンのリモコンを手に取り「自動運転」モードに設定する
- 脚立を用意して、フィルターのホコリを掃除機で吸い取る
- スマホで「電力会社 比較」と検索し、料金シミュレーションを試してみる
電気代の悩みから解放され、家計にも地球にも優しく、そして何よりご自身とご家族が一年中快適に過ごせるように。この記事が、その一助となれば幸いです。


